夫婦別姓を選んだ場合、「子どもの名字ってどうなるの?」と気になる人は多いはず。
結婚前は「別姓OKでしょ」と軽く考えていたけど、いざ名前を決める段階でモヤッとすることも。
この記事では、制度のルールからリアルな「もめポイント」まで、ゆるっと整理してみました。
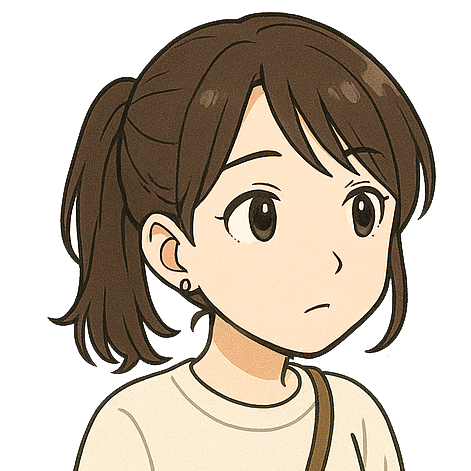
そもそもさ、法律では夫婦別姓できないんだよね?だったら、子どもの名字ってそんなに問題になるのかな…?

ええとこ突くやん。でもな、法律上は夫婦同姓が原則やけど、「通称別姓」ってやり方があるんよ。戸籍上は一緒でも、ふだんは別の名字を名乗れるって仕組みや。

あーなるほど、戸籍上は一緒でも呼び名が違うってことか。たしかにそれだと、子どもの名前とのズレとか、面倒な場面も出てきそう…。

そうそう。実際にはどんなところで困るのか、これから一緒に見ていこか。
「え、子どもの名字って自由じゃないの?」実は結婚時にほぼ決まってる話
戸籍と名字の関係って?「どっちの姓にするか」で将来が決まる
まず前提として、いまの日本では夫婦別姓は法律上は認められていません。
ただし、「通称」として別の姓を名乗ることは可能。その場合、戸籍上では夫婦どちらかの名字を選んで同一姓にする必要があるというルールがあります。
で、子どもの名字ですが……実はこの結婚時にどちらの戸籍に入るかでほぼ決まってしまいます。
つまり、「親と同じ戸籍=同じ名字になる」というのが基本の仕組みなんですね。
あとから子どもだけ変更できる? 家庭裁判所の手続きも存在はするけど…
もちろん「やっぱり名字を変えたい」という場合もゼロではありません。 その場合は、家庭裁判所に申し立てをして子の氏を変更する「氏の変更手続き」があります。
ただしこれは「やむを得ない事情がある場合」に限られ、簡単に通るわけではありません。 また、15歳以上になると子ども本人の同意も必要になるので、現実的にはけっこうハードル高めです。
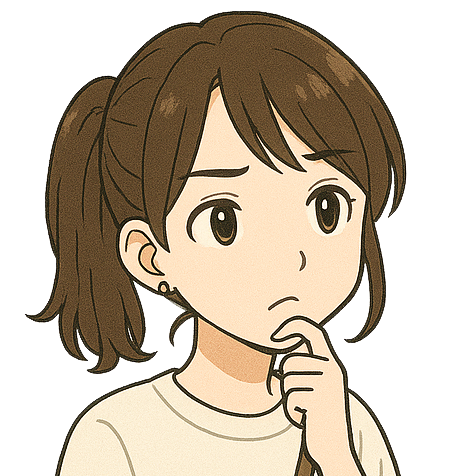
じゃあさ、たとえば夫婦の戸籍は「田中」でも、ママが通称で「佐藤」って名乗ってる場合、子どもを「佐藤」にするのって…できないの?

うーん、基本的には無理やな。戸籍が「田中」なら、子どもも「田中」になるんが原則や。通称を親が名乗ってても、子どもはその通称をそのまま使えるわけやない。

ただし例外として、家庭裁判所で「氏の変更」を申し立てて認められた場合には、子どもを母の姓(通称)に変更できる可能性もあるで。 たとえばこんな場合やな。
- 離婚して母親が旧姓に戻ったあと、子どもを母の戸籍に入れたい場合
- 子どもが社会的にすでにその姓(通称)で呼ばれていて、混乱が生じている場合
- 子ども本人の福祉や利益の観点から、やむを得ないと認められる場合
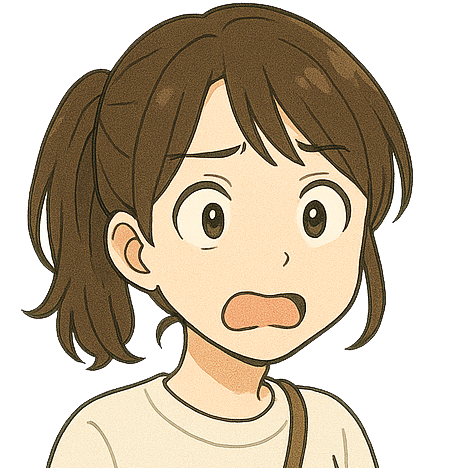
そうだよね、ママが通称で「佐藤」って名乗ってるだけなのに、子どもだけ正式に「佐藤」に変わっちゃったら、それはそれで変な感じするかも…。
ちなみに「夫婦別姓ってどこまでOKなの?」という制度全体のざっくり把握は、こちらの記事でまとめてます
▶ 夫婦別姓、親子別姓ってどこまでOK?できる・できないをゆるっと整理してみた
「名字そろってないとややこしい?」通称別姓の家族でよくあるモヤモヤ
子どもの姓、どっちにする?実は“感情の溝”が出やすい
戸籍上は同じ名字でも、日常では「佐藤」と「田中」を名乗っている夫婦。
このとき子どもの姓をどちらにするかで、実はモヤッとする場面が多いんです。
たとえば、母が「佐藤」として仕事や地域活動に根付いている場合、「子どもも佐藤で統一したい」と思っても、戸籍の都合で「田中」にしかできない。
でも逆に、「書類と普段の呼び方が違うのって混乱しない?」と心配する声も。
なんとなく不自然”とか“周りに説明するのが面倒といった、制度ではなく「気持ちのズレ」がもめごとの原因になることが多いようです。
義実家や保育園で聞かれる「なんで名字が違うの?」の圧
名字が違うことで、第三者からの“ひとこと”に地味に疲れる場面も。
たとえば、義実家から「書類は田中、でも呼び名は佐藤?どっちなの?」と聞かれたり、保育園の先生から「お母さんとお名前が違うんですね」と言われたり。
悪気はなくても、何度も説明するのはしんどいもの。
とくにまだ制度的に別姓家族が一般的とはいえない中では、「うまく伝わらないもどかしさ」がついて回ります。
「やっぱりそろえときゃよかったかも…」という小さな後悔も
子どもが成長するにつれて、学校や医療機関などでのやりとりも増えていきます。
そのたびに名字の説明をするたび、「やっぱり親子で同じ名字のほうがラクだったかも」と感じる人も。
もちろん、別姓であること自体が悪いわけではありませんが、「どうしてこの形にしたのか」を自分たちでも再確認しておけると安心です。

なるほど〜、制度の壁っていうより、周りの目とか、ちょっとした言葉に引っかかる感じなんだね。
「かわいそうって言われるけど…」子ども本人への影響、実際どうなの?
「親と子で名字が違うと、子どもがかわいそう」
そんな声を聞いたことがある人も多いかもしれません。
実際には、通学・病院・書類関係など、親子で名字が違う場面でちょっとした不便が出ることもあるのは事実です。けれど、SNSやブログなどを見てみると「慣れればそんなに気にならない」という声も少なくありません。
子どもが小さいうちは親がフォローできる部分も多く、名字だけでいじめにあったりするケースは稀との声も。
子どもの名字が違うことで起こる地味トラブルが気になる人はこちらの記事もおすすめ
▶ 夫婦別姓で地味に困ることって?病院・学校・マイナンバーなど面倒ごとまとめ!
「海外だとどうしてる?」名字と家族観のちがいをチラ見してみた
日本ではまだまだ「家族=同じ名字」が当たり前の感覚がありますが、世界を見てみるとそうでもありません。
たとえばアメリカでは、夫婦・子どもそれぞれが違う名字でもごく普通。姓に強いこだわりがなく、「名前は個人のもの」と捉える文化もあります。
韓国は逆に夫婦別姓が基本という国ですが、子どもは基本的に父方の姓を名乗るルールがあり、ジェンダー論的な課題が指摘されることも。
国によって「名字」に込める意味合いもルールも違うので、日本のやり方が唯一の正解ではないことが見えてきますね。
「うちはこうしたよ」通称別姓家族の暮らしの工夫
通称別姓で暮らす夫婦のあいだでは、「呼び名」と「戸籍の名前」が一致しないまま家族ができるパターンもあります。
そういった家庭では、名字をどう使うか、どう説明するかについて日々の中で工夫している人も。
- 子どもが小さいうちは戸籍上の名前(例:田中)で書類は通しつつ、普段は「佐藤」で呼ぶ
- 学校や病院などの提出書類には、親の通称姓もカッコ書きで添える
- ある程度の年齢になった子ども自身が「学校では田中、でも家では佐藤」と使い分けている
どれも完璧ではないけれど、「自分たちに合うやり方」を模索してるんですね。

正解は一つやないけど、納得できる選び方はある…ってことやな。
「子どもの名字、どう決める?」制度と気持ちのちょうどいい距離感を探してみる
まず改めて大事なのは、「そもそも日本では、法律上の夫婦別姓はできない」ということ。
だからこそ、通称で別姓を名乗る場合には、戸籍上の名字と、普段の呼び名がズレることが前提になります。
このズレがある中で、子どもの名字をどう決めるか。そのとき考えたいのが、制度と感情と未来の3つのバランスです。
- 制度の枠組み:ルールを先に理解しておくと、あとからの後悔やトラブルを減らせます
- 家族の価値観:名字にこだわる理由は? 誰がどこでどんな思いを抱えているのかを話し合うことが大事
- 子どもの将来像:本人が生きていくとき、どの名前が生きやすいかという視点も忘れずに
いろんな思いが交錯するテーマだからこそ、「どう決めるか」よりも「どう向き合うか」に目を向けてみると、家族に合った形が見えてくるはずです。
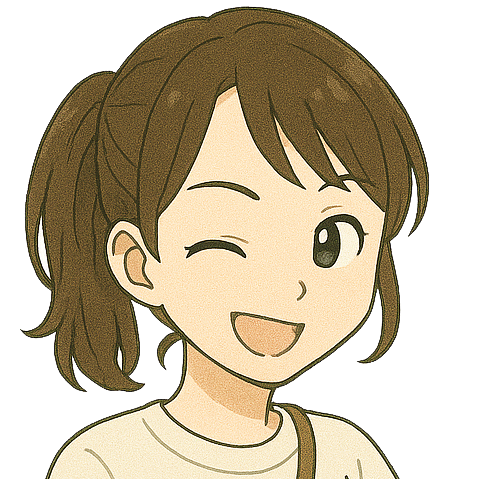
法律じゃ決めきれないからこそ、夫婦や家族の中でちゃんとルールとか想いをすり合わせておくのが大事なんだね。

せやな。そしてもうひとつ大事なんは、子どもが大きくなったときに「自分の名前ってどうなん?」って思ったときに、ちゃんと説明できる選び方をしておくことやと思うわ。

