「eスポーツ=若者の文化」って思ってませんか?
でも実は今、高齢者のあいだでもガチでゲームを楽しむ流れがじわじわきてるんです。
しかも自治体や介護施設が本気でサポートしていたりして…。
今回は、そんな「ゲーマーじいちゃん・ばあちゃん」たちのリアルを、ちょっと驚きつつもリスペクトしながら観察していきます。
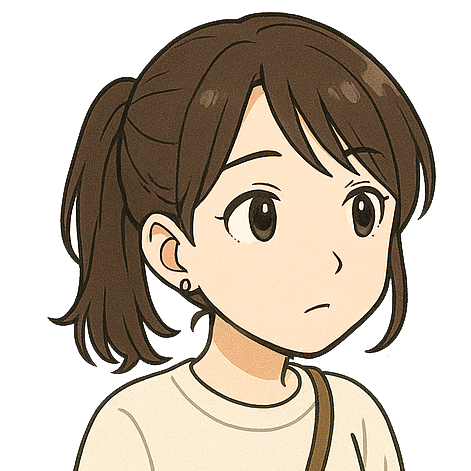
一時期ニュースで高齢者向けeスポーツみたいなの話題になってたけど、今も続いてるの?

それがな、今では自治体や介護施設ががっつりサポートしてて、教室も大会も開かれとるんやで。ちょっとした日常の楽しみになってるんやから驚きやろ?
「マジでやってるの!?」全国で増加中、シニア向けeスポーツのリアル現場
実は全国各地で続々開催中!市区町村単位の取り組み
全国の各地で、シニア向けのeスポーツ教室や大会がじわじわ増えてきています。
たとえば静岡県島田市や熊本市、千葉市、富士見市などでは、自治体主催でぷよぷよ大会や太鼓の達人の体験会などが行われており、参加者も増加中。
交流目的で常設している施設もあるほどです。
どんな人がやってるの?元ゲーマーvsゲーム初心者の割合は?
参加者の多くは、もともとゲーム経験のない人たち。
施設スタッフやインストラクターがついて丁寧にサポートすることで、「あ、意外とできるかも」という体験が広がっています。
一方で、若いころゲーセンに通っていた人が復帰してガチモードになるケースもちらほら。
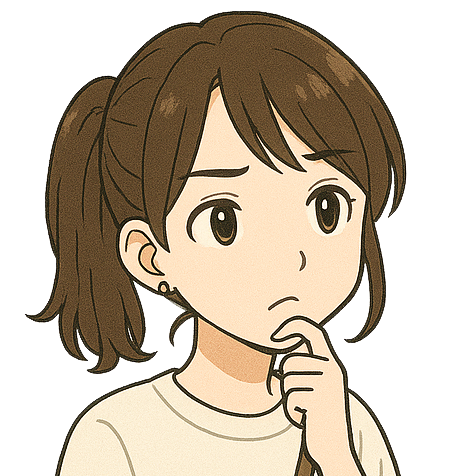
てっきり、元々ゲーマーだった人ばっかりがやってるのかと思ってた。
参加者の男女比は?意外と女性が多いって本当?
男女比でいうと、意外と女性も多いのが現場のリアル。
とくにぷよぷよやリズムゲームは、性別問わず「楽しそう」で入ってくる人が多いようです。
太鼓の達人など、身体を動かすタイプのゲームは、見てても参加しても盛り上がるとの声も。
年齢層は?60代〜80代が中心だけど最高齢記録もすごい!
年齢層としては、60代後半〜80代が中心ですが、なかには90代で現役プレイヤーの方も。
ギネスに載ったシニアゲーマーも海外にはいますし、「プレイ年齢の上限」なんて、もう意味がなくなってきてるのかもしれません。
最近は「温泉付き」「カジノ風」「猫カフェ」など、ここ本当に介護施設?なデイサービスも話題に。
▶ 変わったデイサービスまとめ!温泉・カジノ・猫カフェまで行きたくなる介護施設がすごい!
実はeスポーツも、楽しさ重視な流れでつながってるのかも?
シニア世代が熱中するゲームって?ぷよぷよ・太鼓・グランツーリスモ…意外ラインナップ
反射神経より「思考力」や「リズム感」がカギ
高齢者向けeスポーツと聞いて「格ゲーとかFPSとか、絶対ムリでしょ」と思った人、ちょっと待った。実際に人気なのは、もっと親しみやすいタイトルが多いんです。
たとえば定番は「ぷよぷよeスポーツ」。連鎖を考えるのが脳トレになるとして、教室や大会でもよく使われています。
ほかにも「太鼓の達人」や「グランツーリスモ」など、リズムや操作に没頭できるタイプが支持されてます。
「勝ち負けより楽しい」がモチベの源!
ゲームを通じて交流が生まれることも多く、「勝つより楽しむ」姿勢が根強いのが高齢者eスポの特徴。
プレイしているうちに隣の人と自然に声をかけあったり、「この操作どうやるの?」と教えあったり、そこから雑談が始まることも多いそうです。
単に勝負を楽しむというより、「一緒に盛り上がる」「笑える時間を共有する」ことが目的になっていて、まさに遊びながらつながるスタイル。
年代が違っても、ゲームという共通言語があることで場の空気がぐっとなごむのも魅力です。
プレイしてると自然に笑顔が出てくる、そんなあったかい空気がeスポーツの現場にはあるんですよね。

なんやろな、子どもの頃に友達の家でワイワイ集まってゲームしてた、あの感覚にちょっと近いんかもしれへんな。
FPSやバトロワも!? 一部ではAPEXやフォートナイトに挑戦するシニアも
意外なのが、「FPSやバトロワもやってるシニアがいる」って話。
APEXやフォートナイトを、孫と一緒に遊んでたらハマった…みたいなエピソードも。
もちろん施設の公式導入ではレアだけど、趣味として本格プレイしてる高齢者もちらほらいるようです。

ぷよぷよと太鼓の達人はなんとなくわかるけど…APEXとかってガチじゃん!おじいちゃんつよ…!
「頭だけじゃない?」体と心にも効くって本当!?メリットあれこれ
認知機能・注意力アップ?リハビリや脳活の一環に
eスポーツって、ただの遊びに見えるかもしれません。
でも実は、けっこういろんな面でプラスになるって話があるんです。
たとえば「認知症予防に役立つかも」と言われるのは、判断力や記憶力を使うから。太鼓の達人でリズムに合わせるのも、注意力を使うし、瞬間的な判断も必要になる。
生活にハリが出る?参加者の声や変化事例を紹介
実際に、施設での取り組み後に「表情が明るくなった」「言葉が出やすくなった」なんて声もあるそうです。
それに何より、「楽しい」「やりたい」って思えることがあるのが、心のハリになります。
仲間と一緒に笑ったり、ちょっとだけ勝負してみたり。そんな刺激が、意外と元気の源になったりするんですよね。
でもぶっちゃけどうなの?大人が直面する「つまずきポイント」
ぶっちゃけ操作ムズくない?目・耳・酔い・テンポの壁
「老眼だと画面が見づらいかも」「リズムゲームのテンポについていけないかも」など、そんな不安の声もよく聞きます。
でも実際には、ゲームの画面サイズを調整したり、難易度設定を変えたり、スタッフがついて丁寧にサポートするなど、工夫次第でちゃんと楽しめている人がたくさんいるんです。
グランツーリスモや3D系のゲームで「酔いやすい」という声もありますが、選ぶゲームやプレイ時間を調整すれば大丈夫。
こういう不安があっても、それでも楽しめる工夫があるというのが、今のeスポ現場のリアルです。
ゲーム機材や環境整備って、誰がどうしてるの?
ゲーム機を設置したり、配線を管理したりって、けっこう大変なんですよね。プレイエリアの確保、転倒防止のための動線整理、ゲームごとの機器セットアップなど、意外と細かい手間が多いんです。
加えて、ネット環境やコンセントの位置、音量の調整といった「地味だけど大事な設定」もスムーズに進められるような仕組みづくりが求められます。
とはいえ、最近では地域のボランティアやeスポーツ団体が協力して機材提供やサポートを行う例も増えてきていて、少しずつ現場に優しい環境づくりが整ってきているのも事実です。
「教える人」が足りてない問題
専門のインストラクターや、ゲーム経験があって人に教えられる人って意外と少ないんです。
年齢や体の状態に合わせて、無理なく教えるにはちょっとしたコツや配慮が必要なので、「ただ詳しい人」では務まらないという現場の声もあります。
そのため、自治体や企業では少しずつ研修や育成に取り組んでいますが、現場に十分な人数が行き渡るにはもう少し時間がかかりそうです。
教える側の人材が育つことで、より多くの高齢者が「安心してゲームにチャレンジできる」環境が整っていくはずです。
これからどうなる?自治体×支援×資格でゲーマーじいちゃん時代の予感
支援制度・補助金で導入のハードルは下がる?
ここ数年で支援の体制もじわじわ整ってきています。たとえば、eスポーツ導入に使える「補助金制度」があって、これを活用して機材をそろえたり、プログラムをスタートさせる動きも出てきてるんです。
「機材高そう…」「準備むずかしそう…」というイメージもありますが、そうした不安をサポートする制度があるのはありがたいですよね。
特に地域密着型の施設やNPOなどが、こうした補助制度をうまく使って、日常のレクリエーションにeスポーツを取り入れている例も増えてきました。
最近では、企業や大学と連携してイベントを開いたり、地域のeスポーツ団体が教室をサポートしたりと、ちょっとずつ外部とのつながりもできはじめてます。
「若者の遊び」だったeスポーツが、地域全体の元気づくりに活用されてるって、なんだか未来っぽくて面白いですよね。
トレーナー資格って何?教える人を育てる動き
「健康ゲーム指導士」などの資格制度が出てきており、教えられる人を増やす取り組みも広がっています。
未来の介護施設では、「午前はリハビリ、午後はぷよぷよ大会」なんて日が当たり前になるかも…?と思うと、ちょっとワクワクしてきますよね。
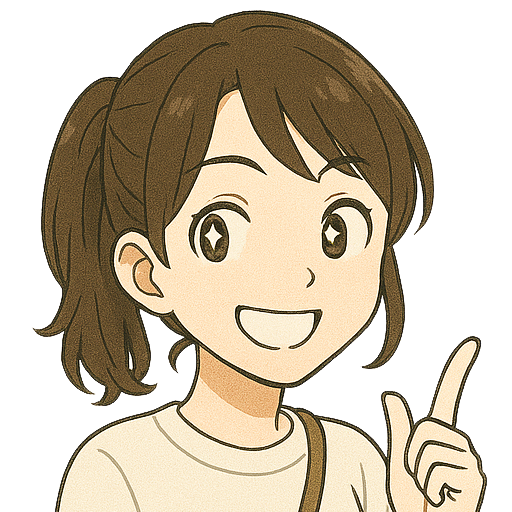
そのうち高齢者向けeスポトレーナーとかって、ちゃんとした職業になってそうだよね。

せやなあ。でも生まれたときからゲームに触れてる世代が介護の現場に入ってくるころには、その高齢者トレーナー職も、あっという間に廃業してるかもしれへんで?自分でなんでもやっちゃう人ばっかりになってさ。

