PPAPって、まだ再生されてるの!?と驚いた人も多いかもしれません。2016年に世界中でバズったあの動画が、実は2024年の今もジワジワと再生回数を伸ばし続けているんです。
ピコ太郎=一発屋と思っていたら、ちょっと見方が変わるかもしれません。この記事では、PPAPがなぜ今も見られているのか?ピコ太郎は今何をしているのか?をゆるっと深掘りしていきます。
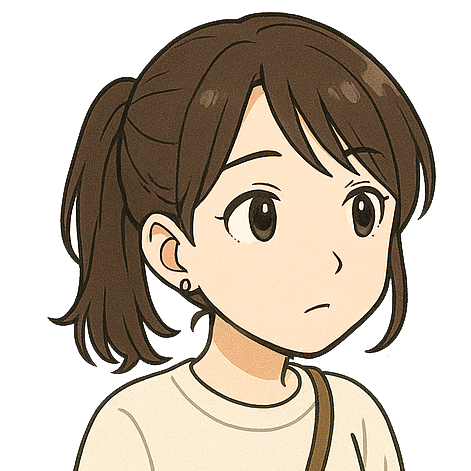
PPAPってさすがにもう過去のネタじゃないの?今でも見てる人いるの!?

そこが意外と終わってへんねや。ちゃんと今もバズの現役なんやで。
PPAPはなぜ世界でバズったのか?|謎の中毒性の正体
2016年、突如として世界中で大流行した「PPAP(ペンパイナッポーアッポーペン)」。その動画はわずか1分にも満たない短さでしたが、あっという間に再生回数は億単位に達しました。
多くの人が「なんでこれが流行ったの?」と首をかしげたはずですが、そこには明確なバズの構造がありました。
中毒性の正体はリズム・短さ・反復
まず、PPAPのリズムは非常にシンプルかつ中毒性のあるビートで構成されています。
1フレーズが短く、すぐに耳に残るリズム感が特徴です。さらに、同じ言葉の繰り返しや動きの反復によって、「見れば見るほどクセになる」構造になっていました。
YouTubeやSNSにおいて、繰り返し見たくなる=シェアされやすいという拡散ロジックと相性抜群だったわけです。
ビーバーの拡散ツイートとインフルエンサー効果
もう一つ大きな追い風となったのが、ジャスティン・ビーバーによる拡散。彼がTwitterで「My favorite video on the internet」とツイートしたことで、一気に海外でも火がつきました。
いわゆるインフルエンサー・ブーストがかかったことで、PPAPはただの面白動画から、見るべきバズ動画へとランクアップしたのです。
「意味はわからんけど笑える」構造の強さ
PPAPの歌詞は英語のようでいて意味がない、でも口に出したくなる。そんな意味のなさが逆に海外では「深く考えずに楽しめる」と評価されました。
言葉ではなくリズムと動きで笑わせる構造は、言語の壁を軽々と飛び越えていったのです。
たとえば、韓国のアーティストPSYによる「江南スタイル」も、似たようなパターンで世界を席巻しました。意味がわからなくても音と動きで笑える、という共通項は、グローバルでウケるエンタメのひとつの型なのかもしれません。
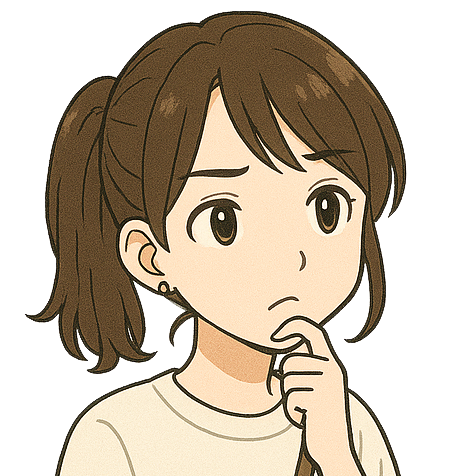
PPAPって、そんなに短い動画だったんだっけ?

「短くて真似しやすい」は、いまのSNS文化にピッタリなんや。そこが強かったんやで。
ピコ太郎の現在|一発屋で終わらなかった理由
あれから8年以上が経った今、「ピコ太郎って今なにしてるの?」と思う人も多いはず。
実は現在も精力的に活動を続けており、一発屋で終わらない理由がちゃんとあるのです。
今更ながら古坂大魔王ってどんな人?“中の人”についてかる~く復習
ピコ太郎の中の人こと古坂大魔王は、実は芸歴30年以上のベテラン芸人です。1990年代には、お笑いコンビ「底ぬけAIR-LINE」として活躍し、「爆笑オンエアバトル」や「ボキャブラ天国」などでその名を知られる存在でした。特にテンポの良いトークと音楽ネタを組み合わせたリズム芸が得意で、そのスタイルはピコ太郎にも色濃く受け継がれています。
2003年にはコンビを解散し、それまで「古坂和仁(こさかかずひと)」の名前で活動していたが、2003年にコンビを解散したのを機に「古坂大魔王」と名を改めてピン芸人として再始動。実はこのタイミングで音楽活動にも本腰を入れており、テクノユニットを結成したり、ライブイベントを主催したりと、音楽家としての顔を強めていきました。
また、2000年代にはあの『マネーの虎』にも出演し、「音楽とお笑いを融合させて世界で勝負したい」と語っていた過去も。その夢が、数年後にPPAPという形で現実化したというのは、まさに伏線回収のようなキャリアです。
PPAP以降、古坂大魔王としての活躍も拡大中!
PPAPの大ヒットをきっかけに、「古坂大魔王」としての活動領域も大きく広がりました。テレビやラジオのコメンテーター、教育や育児に関するイベントへの登壇、地方メディアとのコラボなど、バラエティだけにとどまらない幅広い活躍を見せています。
たとえば、NHKの情報番組『あさイチ』にゲスト出演したり、子育て支援イベント「パパママフェスタ」でトークセッションを行ったりと、ジャンルを問わず柔軟に活動の場を広げています。
芸人としての肩書に加え、音楽家・クリエイター・子育て経験者など、複数の視点を持つ発信者として再評価されているのが特徴です。
現在はタレント業のみならず、裏方としても音楽プロデュースやイベント監修に関わるなど、“一発屋”どころか、むしろキャリアの第2章を謳歌している印象すらあります。

芸名に“魔王”ってつけたときはビックリしたけど…結果的にめちゃくちゃ貫禄ある名前になってるのすごい。
YouTube20周年記念出演・CNNコメント動画
2024年、YouTubeの20周年を記念したスペシャル動画に出演。この企画には、テイラー・スウィフトやエド・シーラン、ジャスティン・ビーバーなど世界的アーティストたちが名を連ねる中、日本からはピコ太郎が唯一の参加者として選ばれるという快挙でした。
さらに、CNNの年始コメントにも起用されるなど、実は「日本より海外」での露出が目立っているのが現状です。
NHK「みんなのうた」など日本での子ども向け路線
日本国内でも地味に活躍を続けており、NHK「みんなのうた」や「いないいないばあっ!」などで楽曲提供をしています。
特に子ども向けコンテンツへの出演は多く、世代を超えて知られる存在に変化しつつあります。
地味に続いていた音楽活動とプロデューサー業
そもそもピコ太郎の正体である古坂大魔王さんは、ピコ太郎のブレイク以前から、お笑い芸人をやりながら音楽家としても活動していました。
その流れをくんで、今も音楽制作やプロデュース業は継続中。最近ではクラシックピアニストの角野隼斗(かてぃん)とのコラボなども行っています。
なぜPPAPは今も再生され続けるのか?
PPAPの公式動画は、2024年現在で7億回再生を突破。しかも、その再生数は今もジワジワと伸び続けているというのだから驚きです。
その理由を掘り下げてみましょう。
TikTokやショート動画との親和性
PPAPの尺は約45秒。これはTikTokやYouTube Shortsといったショート動画文化にぴったりの長さです。
しかも、PPAPがバズった2016年当時は、まだTikTokも一般的ではなく、ショート動画文化が今ほど浸透していなかった時代。そんな中で“短くてテンポが良く、真似しやすい動画”として自然に拡散されたというのは、今思えば先取りだったとも言えます。
たとえば、韓国の「江南スタイル」や、アメリカの「What Does the Fox Say?(The Fox)」といったミーム動画も、当時としてはショート動画的な構造でバズった先駆け的存在。PPAPもまたその文脈に連なる、早期ショートネタのひとつだったと言えるでしょう。
若い世代が「ちょっと面白いネタをサクッと見る」「マネして投稿する」という流れと相性が良く、二次拡散が続いている構造です。
英語教材・子ども番組での定着
PPAPはシンプルな英語表現とリズミカルな構成のため、英語教材として使用されたり、子ども向け番組で流れたりすることも。
「子どもに見せても安心」「言葉の勉強になる」として、家庭や学校現場での活用例もあります。
「海外ではリスペクトされる一発ネタ」という文化的違い
日本では一発屋として消費されがちなネタも、海外では「一度バズればレジェンド」扱いされる傾向があります。
ピコ太郎もそのパターンで、「懐かしいのに今でも笑える」ネタとして再評価されているのです。

海外って、ホンマに一発ネタに優しい文化やな。日本やと消費されて終わりやけど、向こうはレジェンド枠に昇格するんやで。
ピコ太郎の海外人気は今も健在?
海外では、ピコ太郎は未だに“Funny Japanese guy”として認知されています。
むしろ、今の方が「文化として定着している」感すらあります。
観光地やイベントでの外国人の反応
たとえば、2024年4月に三田警察署の「一日警察副署長」を務めた際には、都内観光に来ていた外国人観光客が大喜び。「ピコ太郎だ!」と歓声が上がり、一緒に記念撮影を求める列ができたほどです。
そのほか、東京スカイツリーでのイベントや空港でのプロモーションにも出演しており、観光地と日本カルチャーをつなぐ顔としての役割も果たしています。
メディア・企業コラボの海外比率
出演やコラボの依頼が、ここ数年は日本より海外の方が多いという現象も。
YouTubeやNetflixの特番など、国際的な舞台での露出が続いているのが特徴です。
日本よりも海外の方が温度が高い現象
日本では「もう古い」とされがちなネタでも、海外では「懐かしい=名作」として扱われがち。
ピコ太郎は、そんな温度差の恩恵を受けている珍しいパターンの芸人と言えるでしょう。
PPAPは時代遅れじゃない?|再評価される理由
一度は過去のネタとされながらも、PPAPは今も各地で見直されています。
それは、バズの設計が「一時的な流行」に留まっていなかったから。
ノスタルジー消費とレトロネタの循環
SNSやYouTubeでは、数年前のネタが突然再評価されるノスタルジー再燃の波が定期的にやってきます。
PPAPもそのサイクルにうまく乗っており、「なつかしい」「これ好きだった」といった投稿が再ブームを支えています。
「わかりやすさ」は何年経っても武器
結局、言語や国境を超えるコンテンツにはわかりやすさが必要です。
PPAPは難解な設定や背景を一切排除している分、誰でも直感的に笑える。「説明不要」の強さがあるのです。
さらに、近年のバズ文化では「誰が見てもすぐ笑える」ことが命。
子どもたちが真似し、動画にし、SNSで拡散する。
そうした感覚優位の評価軸にも、PPAPはしっかりハマっていたというわけ。
たとえば最近では、「チグハグなダンスCM」や「棒読みすぎる商品紹介動画」が逆に面白いと話題になった例もあります。内容の完成度よりもわかりやすくて真似できることが、拡散の決め手になっているのかもしれません。

PPAPって、ただの一発ネタかと思ってたのに…今やレジェンド枠とか、まさにアメリカンドリーム!今後もいろんなところで再活用されそうな感じがするよね。

せやな。1分動画が数億再生って、もはや笑える資産や。
