SNSでよく見かける「ほならね理論」って、なんとなく意味はわかるけど、ちょっとモヤッとしません?
たとえば「ほんならお前がやってみろよ」みたいな返しのことだと思うけど、それって正しい主張なのか、それともただの逆ギレなのか…悩むところですよね。
ネットでは便利なツッコミとしても使われる一方で、誰かが本気で使うと炎上したり、論破扱いされたり…と何かと空気を読まれるワードでもあります。
この記事では、「ほならね理論」の意味・元ネタ・なぜモヤるのか、誰が使ってるのか、さらには言われたときの対処法まで、SNSで浮上しがちなこの言葉をまるっと解説します。
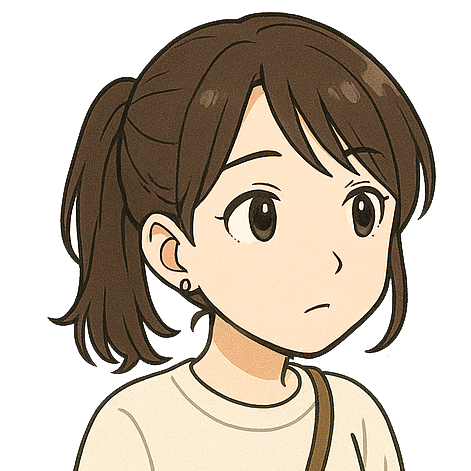
最近ほんとよく見るけど、正直ちゃんと意味はわかってないかも…!

せやろ?よう見かけるけど、意外と説明できる人少ないんや。「正論」か「詭弁」かでモヤモヤするポイントも多いしな。ほな、順番に見てこか。
「ほならね理論」って何?言葉の意味から確認
「ほならね理論」は、ざっくり言えば「文句言うなら自分でやってみろや」という主張のこと。
つまり、相手の批判や意見に対して、「じゃあお前がやれよ」と返す逆説スタイルの言い回しです。
関西弁の「ほならね(=それならね)」が語源で、元々は軽い冗談や皮肉として使われることも多い言葉。ただし、ネットでの使われ方ではちょっとニュアンスが変わってきています。
一見、筋が通ってるようにも聞こえるこの理論。でも、実際には「詭弁(論理的に見えて論理じゃない主張)」として扱われることも多く、議論の場での使い方には注意が必要です。
元ネタはsyamu&シバター、なんJで浸透
この言葉がネットで定着した背景には、YouTuber「syamu」の存在があります。動画の中で「ほならね、自分でやってみろって話ですよ」と逆ギレ気味に反論したセリフが元ネタとして有名です。
その後、格闘系YouTuber「シバター」やなんJ界隈などで、揶揄的に使われるようになり、一種のネタ化。そこから「ほならね理論」として、ネットミーム的に広がっていきました。
つまり、言葉としての「ほならね理論」は、最初から正論ではなく、皮肉や煽りとしてのニュアンスを含んだ文化的背景があるというわけです。
言ってみたくなる理由って?正論っぽいのモヤるわけ
「ほならね理論」は、たしかに言いたくなるフレーズ。だって、自分が一生懸命やってることに対して無責任な批判をされたら、「じゃあお前がやれよ!」って言いたくなりますよね。
でもこの理論がモヤるのは、立場の非対称性があるから。たとえばプロが素人に向かって「ほならね」と言うと、上下関係を強調してしまって、余計に「感じ悪い」印象になりやすい。
また、論点をすり替えるように見えることもあり、「本題を避けてる」「責任転嫁してる」と見なされる場合も。
だから、使い方を間違えると正論っぽい詭弁として炎上しやすいんですね。
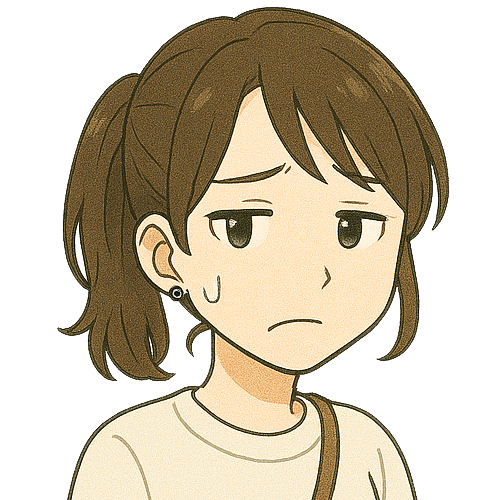
あー、わかる。言いたくなるけど、使う人によってウッてなるときあるかも。
誰が使ってる?粗品・橋下・キタニタツヤ…大人も使うフレーズ
粗品・芸人系
お笑い芸人・霜降り明星の粗品は、テレビでの発言やYouTubeで「ほならね」系のツッコミを使うことがあり、視聴者の間でも話題に。
芸人の場合はネタとして成立しやすいですが、冗談か本気かが読み取れない場面では炎上の引き金になることも。
政治家・橋下・丸山
元大阪市長・橋下徹さんや、丸山穂高元議員など、政治家が「ほならね」に近い理論で批判に返した例も。
特に「じゃああなたがやってみてください」といった返しは、建設的に見えることもあれば、「議論をシャットアウトしてる」と批判されることも。
クリエイター・キタニタツヤetc.
アーティストのキタニタツヤさんも、SNSで「素人にとやかく言われるのが一番ムカつく」と発言し、ちょっとした炎上に。
意図としては共感できる部分もあるものの、クリエイターとリスナーという立場の差によって見下してる感が出てしまうと批判されがちです。
「言われた時どうする?」知恵袋的リアル返し方比較
「ほならね理論」をぶつけられたとき、どう返すかは人それぞれ。でもよくあるパターンはこんな感じ。
- 冷静に立場を整理して返す(「私は素人だけど、感じたことを言っただけです」)
- 実行してみる(実際に自分でやってみるという選択)
- スルー&ブロック(ネットだとこれが多い)
あるいは、「じゃあ一緒にやってみますか?」みたいに返せたらスマートかも。
反撃せずにユーモアで受け流すのも、ある意味ネット強者の技です。
使うべきでない場面は?古い・ウザいって思われるタイミング
「ほならね理論」は便利だけど、どこでも使っていいわけじゃありません。特に避けたいのはこんなケース。
- 相手がすでに経験者(=やった上で言ってる場合)
- 感情的なやりとりの最中
- 空気がピリついてるSNSの場面
こうした状況での「ほならね」は、ただの逆ギレや責任逃れにしか見えなくなることも。
ネタとして通じる相手かどうか、空気を読むのが大事です。
まとめ:自分のほならね理論との付き合い方
「ほならね理論」は、うまく使えばツッコミとして便利。
でも、どこかで上からに聞こえたり、逃げに見えたりもする。だからこそ、大事なのは場の温度感と、相手との関係性。
言いたくなる気持ちもわかるけど、軽いネタには軽く、重い場面ではスルー。そんなさじ加減を持っておくと、SNSでもちょっと強くなれるかもしれません。

ていうか、そんなに文句あるなら自分でやってみたらいいのにね〜?
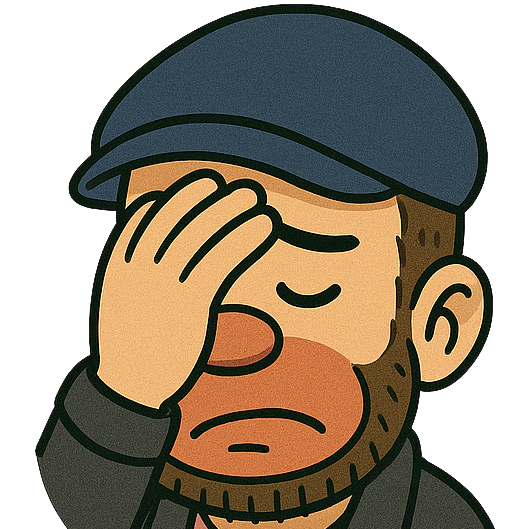
それ、見事な「ほならね理論」やで。
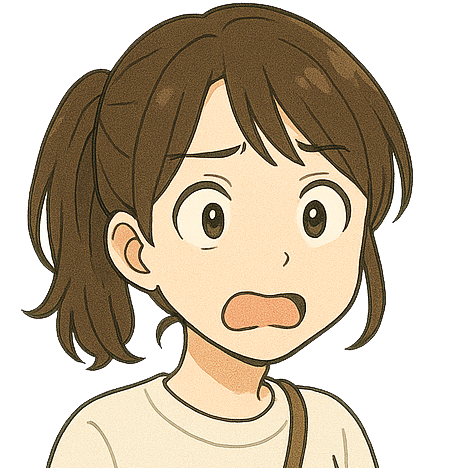
あっ……言っちゃった!?

うん、きれいにキマったで。
